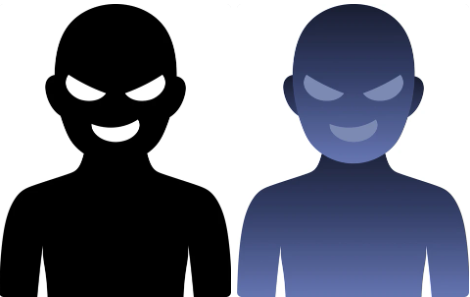
長崎市の70代女性、1900万円をだまし取られる
長崎県内でニセ電話詐欺の被害が急増しています。特に深刻なのは長崎市の70代女性のケースで、約1900万円という巨額をだまし取られました。この事件では、巧妙な段階的な手口が用いられました。
被害の流れ:
- 最初に「インターネットセンター」を名乗る男から「あなたは犯罪の被害にあっている」との電話
- その後、兵庫県警を名乗る男らが電話やLINEで接触
- 「お金を調べるため」と称して指定口座への振込を要求
- 女性は合計1892万円を振り込んでしまう
幸いにも、女性が金融機関に相談したことで詐欺が発覚しましたが、すでに巨額の被害が発生していました。
若年層もターゲットに – 佐世保市の20代男性事例
驚くべきは、被害者が高齢者に限らないことです。佐世保市では20代の会社経営者の男性が約240万円の被害に遭っています。
このケースの手口:
- SNSや電話で接触してきた融資会社に1000万円の融資を依頼
- 「送金前に100万円が必要」などと偽りの理由をつけて振込を要求
- 結果として約240万円をだまし取られる
増え続ける詐欺の特徴と対策
警察によると、最近の詐欺には以下の特徴があります:
- 権威をかたる:警察や金融機関、政府機関を名乗る
- 緊急性をあおる:「すぐに対処しないと大変なことに」と焦らせる
- 段階的接触:最初はささいな要求から始め、次第に金額を増やす
- 多様な通信手段:電話だけでなくLINEやメールも活用
詐欺を見破るためのポイント
- 個人名義の口座を指定してくる:公的機関や正当な企業が個人名義の口座を要求することはありません
- 前金を要求する:融資の前に手数料などを要求するのは危険信号
- 相手が焦らせる:時間的プレッシャーをかけてくる場合は要注意
暑い夏こそ増える在宅時の電話詐欺
今年の猛暑で家にいる時間が増えるため、電話詐欺のリスクが高まっています。特に高齢者の一人暮らし世帯は狙われやすい傾向にあります。
予防策:
- 不審な電話がかかってきたら家族や近所の人に相談
- 公的機関を名乗る電話には直接その機関に確認(公表されている番号からかけ直す)
- 金融取引には必ず第三者と相談する習慣を
まとめ:情報共有と警戒心が被害を防ぐ
長崎県内で発生しているこれらの事件は、全国どこでも起こり得る典型的な詐欺手口です。被害を防ぐには、最新の詐欺情報を共有し、不審な接触に対して常に警戒心を持つことが重要です。特に高齢の家族がいる場合は、定期的にこうした詐欺の手口について話し合うことをおすすめします。
「もしかして詐欺?」と思ったら、ためらわずに警察(#9110)や消費者ホットライン(188)に相談しましょう。小さな疑問が大きな被害を防ぐことにつながります。
Let’s redoing!
#詐欺被害 #貧困層 #マイノリティ #弱者 #人権 #年収 #障害者 #ビジネス #再スタート #挑戦 #言葉