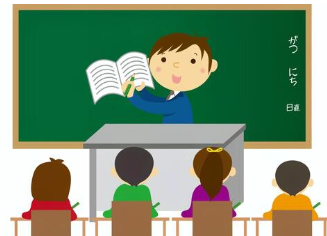
信じられない事件が島根県の小学校で起きました。教師が生徒が授業で育てた米を勝手に持ち帰り食べていたのです。教師の資格どころか、人間としての倫理観を疑うような行為に、言葉を失います。
■事件の概要
松江市と安来市の小学校に勤務していた20代の男性教諭は、昨年10月に児童が収穫した米30キロのうち、約20キロを自宅に持ち帰り食べていたことが発覚しました。この米は地域の代表者から学校に寄贈されたもので、児童たちの学習成果の証でした。
■隠蔽と発覚
教諭は児童に配る予定だった玄米を家庭科室に放置。年度末に精米して自宅に持ち帰りました。事件が発覚したのは、新年度に異動した後、元同僚の教諭が家庭科室に残された米ぬかや精米機に気付いたからです。
■教師の言い分
県教委の聞き取りに対し、男性教諭は「報告すると怒られると思った。配るのを怠っていたので、ごまかそうと思った」と説明。米価格高騰を動機とした発言はなかったと報告されています。
■処分と対応
教諭は11日付で停職3か月の懲戒処分となり、同日付で辞職しました。「児童や保護者、関係者に申しわけない。教員を辞めるなど何かしらの責任を取らないといけない」として自ら辞職願を提出したのです。
■教育行政の危機
県教委はこの行為を「県民の教育行政への信頼を失わせる行為」とし、服務規律確保の徹底などを文書通知。研修会などを通じて再発防止を図るとしています。
■背景にある社会問題
確かに、米価格の高騰や低賃金・物価高といった経済的な圧力は社会に蔓延しています。経済的困窮が治安悪化を招くことは歴史が証明しています。しかし、教育現場でこのような情けない事件まで起こるとは予想できませんでした。
教育者は子どもたちに道徳や倫理を教える立場にあります。その教育者が子どもの成果を横領するような行為に及べば、教育そのものの信頼が揺らぎます。たとえ経済的に厳しい状況であっても、越えてはならない一線があります。
この事件は、単に一個人の不祥事ではなく、教育現場の服務規律や監督体制、さらには教員の労働環境やメンタルヘルスを含む、より深い問題を浮き彫りにしています。島根県教委には、再発防止のための実効性のある対策を強く求めます。
Let’s redoing!
#詐欺被害 #貧困層 #マイノリティ #弱者 #人権 #年収 #障害者 #ビジネス #再スタート #挑戦 #言葉